
最近何かと話題になっている早期教育。子どもが将来幸せに暮らせるように早期教育が必要かを考えている親御さんも多いのではないでしょうか?
今回はTwitterの投稿を独自分析することで見えてきた情報から早期教育が必要かどうかについて考えていきたいと思います。
教育学部出身の2児のママ。学んできた専門知識や日々の生活での経験を活かして分かりやすく子どものためになるような情報を発信しています!
●早期教育はどのような時に必要になるか
●早期教育を行なう上での注意点
早期教育は勉強習慣の土台を作るためには必要

早期教育に対するポジティブ派の意見とネガティブ派の意見の双方をしっかりと見て判断した結果、私の結論は「早期教育は勉強習慣の土台を作るためには必要」だと感じました。
早期教育の必要性を考えるうえで重要なポイントは、早期教育に何を求めているのかだと思います。
例えば、「私の子は2歳で九九が全て言えます!」というような結果を重視した早期教育なのであれば私は反対ですし不要だと思います。
逆に、「学校で英語の学習が始まるまでの間に英語に抵抗感が無いように勉強を楽しめる土台を作ってあげたい」というような過程を重視した早期教育なのであれば賛成ですし必要だと思います。
子どもに負担があまりかからないようになるべく楽しみながら勉強の習慣を付けてもらうというのは正直親にとってはとても大変だと思います。放任の方が楽であることは言うまでもないでしょう。
ただ、大変ですが子どもの将来のことを思えばそれだけ頑張る価値はあるのだと思っています。
生まれながらにして持っている潜在的な能力値は子どもによってばらつきがあると思います。
生まれながらの能力はどうしようもできませんが、勉強習慣の土台を作ってあげることで挽回はしっかりできると信じています。イメージとしては以下のような感じです。

潜在的な能力が高ければ誰にも負けないような物凄い能力になるかもしれませんし、潜在能力が低かったとしても勉強習慣を整えてあげることで平均以上まで引き上げることが期待できるでしょう。
とはいえ、これはあくまで私の価値観であって価値観は十人十色です。
今回の記事では、ポジティブ派とネガティブ派のどちらの意見にも触れてこの記事を読んでいる皆さんご自身の答えを見つけてもらうことが目的ですので、是非皆さんなりの答えを探してみて下さいね!
Twitterから分析した早期教育に対する印象

2023年3月にTwitterに投稿されていた早期教育に関するツイートを100人分収集をして分析をしてみました。
分析方法は、ツイートの内容を「ポジティブ」、「中立」、「ネガティブ」の3つに分類をしてその割合を求めていきました。
結果はこちら。

ポジティブが53%、ネガティブが35%、そして中立が12%という結果となりました。
ポジティブな意見がかろうじて過半数を占めていたものの、ネガティブな意見も3割以上を占めているため賛成派と反対派がどちらも多数いることが分かりました。
それでは、それぞれの立場の意見について詳しく見ていきましょう。
早期教育にポジティブな印象を持ってる人たちの意見
早期教育、子どもの自由さを奪うのでは?って心配してたけど、毎日おしりのダンスとかライオンのダンスとか創作してるしこの程度で奪われるようなものではないみたい🤣
— まりん@2y8m+🤰(9月予定) (@lizzy_lars) March 26, 2023
早期教育を始めようかと思っている方でも「子どもに悪影響は無いのかな…」と心配される方もいますよね。
こちらのツイートをされた方も始めは子どもの自由さを奪うのではと心配していたようですが、無邪気な子どもの姿を見て子どもの適応力が高く心配が吹き飛んだようですね。
過度な教育(スパルタなど)は子どもに悪影響を与える可能性は高いと思いますが、子どもの気持ちを尊重して無理なく進める分には問題無いのかもしれませんね。
私たちが想像する以上に子ども達の適応力って素晴らしいのでしょうね!
ママは知育や早期教育への興味すごいけど、息子はかなり急な滑り台も逆走で登り切って周りのファミリーに「おぉ…!」と驚かれるような肉体派なので、彼の才能はそちらにあるのかもしれない。
だとしても、できれば子も親も無理しすぎずに学習習慣をつけて、将来の選択肢が増えるようにしてあげたい…— ねるね*1y2m🦖DWE (@__yuru11) March 26, 2023
早期教育にポジティブな印象を持っている方の多くは、「将来の選択肢を増やしてあげたい」という想いを持っていますよね。
早期教育というと、「お受験のためのお勉強!!」というイメージもあったりしますが、実は世間の方はそれよりもお受験はしなくとも将来的に子どもが進みたい道に進ませてあげたい、その土台を作ってあげたいと思っている方が多い印象です。
勉強が嫌いよりも勉強にあまり抵抗が無く、学力があった方が将来の選択肢が増えるというのはその通りかもしれませんね。
早期教育、小受、ディス親いるけど、、、私はぜんぜんやらせるかな。子どもに強要したくない、親のエゴって言われるけど、うまくやる人は失敗したフォローも考えてるだろうし、勉強習慣や価値観、学歴は足引っ張らないと思う。私は放任でのびのび育ったから、勉強大事と気付いてからでは遅かった。
— miyu (@miyu_miyu_0520) March 16, 2023
早期教育を通して、勉強習慣や価値観や学歴が付くことは子どもの将来にとってマイナスにはならないというご意見ですね。
放任でもそのうち勉強の大切さに気が付くことはあるかもしれませんが、確かに親がフォローをして勉強習慣や価値観を学ぶレールに乗せてあげる場合と比較すると遅くなる傾向にありそうですよね。
世間を見てみても、「もっと学生の時に勉強しておけば良かった!」と大人になってから勉強の大切さに気が付いたという方も見かけます(就活では「学歴フィルター」みたいな言葉もあるくらいですからね…)。
放任は親としては楽かもしれませんが、「子どもが迷子にならないようにしっかりと勉強習慣のレールに乗せてあげる」というのは親として大切なことなのかもしれませんね。
それと勉強を楽しくさせる程度なら両立出来ると思うので、それくらいの早期教育はメリットあると思ってます、
いろんな意見があるんでしょうけど、後で勉強楽しいと感じさせるのは難易度高いかなと。— ryuji (@jMQfg53UiZ4TS3d) March 8, 2023
こちらのツイートも早期教育のメリットとして「勉強に対する抵抗感を無くす」という点にフォーカスされています。
確かに大きくなってから「勉強を好きになれ」といきなり言われても確かに軌道修正はなかなか大変な子が多いと思います。
あくまで私のイメージですが、勉強が嫌いになる一例として以下のようなイメージを持っています。
放任
↓
勉強より遊びが楽しいので遊ぶ
↓
勉強が出来なくなる
↓
勉強がつまらない
↓
勉強より遊びが楽しいので遊ぶ
↓
(以下、ループ)
私の場合は、普段の授業が理解できる時は、「楽しい!」と感じますが、全然分からない時には苦痛でしかありません…
当然、その科目は苦痛なので勉強をする気にもなれずにどんどんと苦手になっていく…という感じです。
ですので、子どもの時のように色々なことを受け入れることができる時に勉強を楽しくさせるような早期教育であればその必要性は大きいのかもしれませんね。
長男の習い事のクラス100点満点の子が多くて平均点も高い👀📚英語の早期教育って効果あると思います😘
学校、塾と英語の3本柱でこの1年終わり🏫明らかに現代の子はマルチタスク💻
好きな社会(地理と鉄道)を伸ばしつつ家庭でできることを最大限に経験させてあげたい😊 #めちゃハード pic.twitter.com/iUpXB4GPF4— miku hirata♥️平田未来 (@mikuhirata) March 19, 2023
こちらは実際にお子さんを英語の早期教育に通わせているお母さんの投稿ですね。
特に日本人は恥ずかしがり屋さん?なので、外国人と英語で話す機会があったとしてもあまり積極的に話にいけない方も多いのではないでしょうか?
小さい子の場合、良い意味で怖いもの知らずで「恥ずかしさ」が邪魔をしないで英語を学べるので、大人から勉強を始めるよりもアドバンテージがある可能性がありますよね。
実際に効果を実感しているというのも参考になるご意見です。
2020年度より、小学校では3.4年生で英語活動、5.6年生では教科として英語が取り入れられるようになりました。 小学校で英語を取り入れることに対して、更には早期教育に関して、未だに賛否が分かれていますが、英語教育はいつ …
早期教育にネガティブな印象を持っている人たちの意見
早期教育受けたからと言って将来優秀な人間になるとはならないよなぁ。非認知能力を鍛えた方が良い気がする。旦那、早期教育受けたタイプの人だけど全く料理できないし家事の要領悪い。自分で「仕事できないから残業してる」って言ってるし。勉強はできるんだけどね…
— とめ子 (@TomekoTomekooo) March 26, 2023
能力には学力など数値で測ることが可能な「認知能力」と協調性や計画性や自制心など数値で測ることが難しい「非認知能力」に分けることができます。
こちらのツイートでは、将来優秀な人間になるためには早期教育で認知能力を鍛えるよりも非認知能力を鍛えた方が良いのではないかという内容ですね。
確かに社会で活躍している方々を見てみると学力だけではなく、人間性の部分も相当大切な気がします。
学力のみを伸ばす早期教育だけではなくしっかりと非認知能力も伸ばせる教育が重要そうですよね。
まぁ、訓練したら早めに出来るようなる子もいるが、時期がくればさほどの労力を要さずともそのうち出来るようになるものを、わざわざ負荷をかけてまで早めにやらせる必要があるか否かという話でもあり…… 早期教育全般そういう話だが。
— 👻4y (@chi_mama__) March 21, 2023
時期が来ればさほどの労力を要さずにそのうち出来るようになるので早期教育は不要では?というご意見ですね。
例えば、九九を3歳で覚える場合と8歳で覚える場合を比較すると8歳で覚える方が苦労は少ないのでは?というお話ですね。
確かに上の例の場合は「九九を覚える」ということのみにフォーカスするとその通りだと思います。
ただ、ポジティブ派の意見を見てみると早期教育の位置付けとしては、「九九を覚える」というよりは「勉強に抵抗感を持たないように」という部分にフォーカスされている気がします。
つまり、「楽しく九九を覚えた」と「苦痛だったけどなんとか九九を覚えた」では、どちらも「九九を覚えた」という結果は同じですが、結果に辿り着くまでの過程が「楽しい」と「苦痛」で正反対になるということですね。
この違いが、早期教育の必要性を考える上でのポイントとなるのではと思っています。
ちょっと人より頑張ればちょっとだけ早くできるようになるのかもしれんけど、たまたまそれが得意な子と同じ程度なら多分そのうちみんな追いつくでしょ。
早期教育ってそんな意味あるんかなぁって正直思う。— にゃふらっく (@nya_hu) March 14, 2023
こちらは、早期教育で一時的に早く覚えることができたとしても結局最終的にはみんな追い付くわけだしあまり早期教育に必要性を感じないというご意見ですね。
先ほどと同じく、過程というよりは結果にフォーカスしているご意見かと思います。
結果を重視するのか、それとも過程を重視するのかは人によって価値観が分かれる部分ですので、どちらが正しいうのはあまり無いかと思っています。
また、実は時間軸についても意識をする必要が出てきます。
時間軸が短ければ短いほど追い付ける確率が上がりますが、時間軸が長くなると追い付ける確率が下がってしまうことですね。
英語の勉強を1時間だけした子には追い付けそうですが、100時間した子に追い付くのは大変そう…というイメージです。
ピアノじゃないですけど幼稚園が早期教育系だったのでもう座っているのが苦痛で苦痛で仕方なかったです。かしこくはなりませんでした。
— kyo04132 (@kyo04132) March 11, 2023
実際に早期教育を受けた方の貴重なご意見ですね。
幼稚園で早期教育を受けて苦痛だった上に賢くはなれなかったという経験談をお話されています。
早期教育は「過程」を重視するため、結果にこだわって子どもに苦痛を与えてしまうと逆に勉強が嫌いになってしまい元も子もなくなってしまいます。
投稿者のお話では早期教育の過程で苦痛を感じている様子がうかがえるので、苦痛を感じてしまうような早期教育は結果が出ない可能性があることが分かりますよね。
「生徒たちは事実の羅列を復唱できるようになるが、それを理解することはない。事実は何の役にも立たないまま じっと記憶に居座り、自分の力で考える能力を破壊する。子供達に自分の経験とは縁のない情報を学ばせるのは、人間性に対する攻撃に等しい。」
暗唱・暗記系早期教育の弊害…!— マリエ (@marie00812) March 13, 2023
先ほども少し触れましたが、早期教育を「過程」ではなく「結果」だけで考えてしまうと様々な弊害があり、まさにこのツイートの通り「自分で考える能力を破壊する」ということにも繋がってしまうかと思います。
私自身、勉強をしていて楽しいと感じる瞬間は、「あ、そういう仕組みなのか!!もやもやしていたけど、スッキリした!!」と思った時です。
つまり、よく分からずにただただ暗記だけをしている時は特に楽しいとは感じないということですね。みなさんはどうでしょうか?
早期教育をするにしても、「2歳で九九が出来ました!!」というのは、結果を重視した暗唱・暗記系で子どもが楽しいと感じていない可能性があったりするので注意が必要そうですね。
早期教育を行なう上での注意点
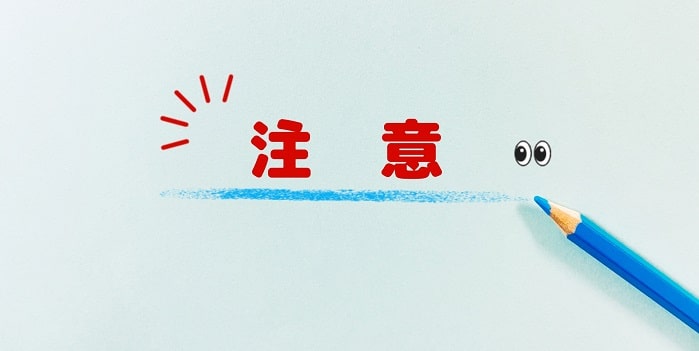
ポジティブ派とネガティブ派の意見を総合して判断すると早期教育を行なう上で注意すべき点も見えてきます。
細かい部分を挙げれば色々とあるのかもしれませんが、「早期教育は子どもの勉強に対する抵抗感を無くすこと」という意識を忘れないことが最も重要な点だと感じました。
「私の子は2歳で九九ができるのよ、凄いでしょ!」みたいな感じで親がマウントを取りたいだけで行っているような早期教育は子どものためというよりは、もはや親のエゴになってしまいます。
「勉強に対する抵抗感を無くす」というのは、つまり子どもが「勉強って楽しい!」と思えるような環境を整えることです。
そして、その子の性格によってどのようなアプローチで「楽しい!」と思ってくれるかが違うので、そこが親御さんの腕の見せ所になるかと思います。
例えば、ジッとしているよりも体を動かすことが好きな子であれば、体を動かしながらでも学べるような早期教育が良いでしょうし、逆に多くの子と関わるよりも静かにしていることが好きな子であればじっくりとお家で一緒に勉強をしてあげるのが良いでしょう。
どのようなアプローチが正解かは色々と試行錯誤をして子どもの様子を見ながら探っていくことになりますので、親御さんとしては大変かもしれません。
ただ、子どもが「嫌だ…」と感じるような早期教育を続けてしまうと逆効果になるおそれもあるので、注意すべき最も重要なことだと思います。
まとめ
今回は早期教育が必要かどうかについてTwitterに投稿された皆さんの意見から考えていきました。
反対派の意見の人も賛成派の意見の人もどちらも子どものことを考えて早期教育がどうなのかを考えているのでどちらの意見も共感できる部分があるかと思います。
私は早期教育については子どもに負担をかけすぎないという条件であれば賛成なのですがみなさんは両方の意見を聞いてみてどう感じましたか?
いずれにせよ子ども達のことを第一に考えたいですよね!
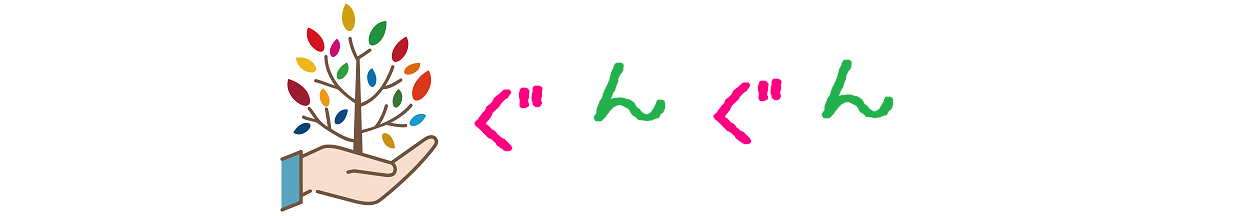

からスタートしました!-min-700x401.jpg)




