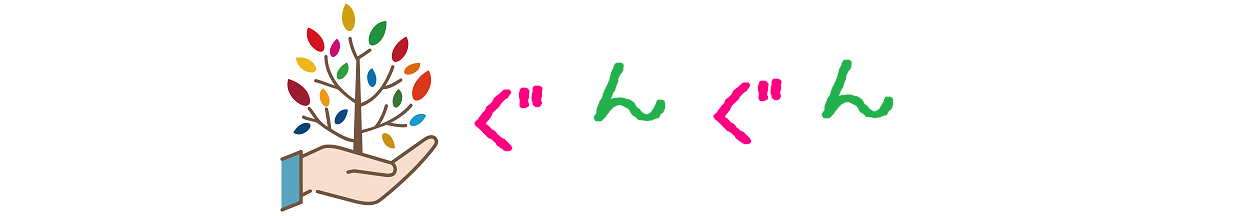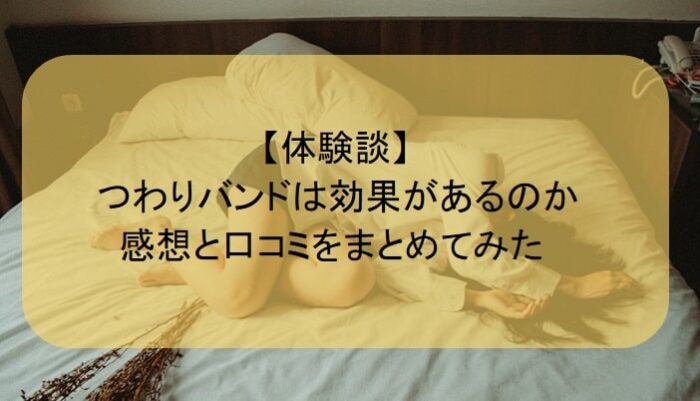1歳になると、歩き始めたり喃語 が増えたりとますます可愛くなってきますよね!
それなのに、なんだか怒ったり泣いたり、癇癪を起すことが増えた気がしませんか?
「イヤイヤ期は2歳あたりからのはずなのに、なんで…?」
今回は、1歳から増え始める癇癪について書いていきたいと思います!!
癇癪は親のせい?

では早速ですが、1歳の子が癇癪を起すのは親のせいでしょうか?
2人の子を育てている経験から言うと、親のせいで癇癪を起している場合もあると思います。
この後で詳しく書きますが、癇癪を起こす原因として大きく3つ挙げることができます。
①親の対応や関わり方
②子どもの発達
③環境や体調
この3つのうちの①と③に関しては、親が気を付けたり工夫することで癇癪の頻度を低くしたり、癇癪を起しても早めに気持ちを落ち着かせることができます!
癇癪の原因と対応法
1歳の子が癇癪を起す大きな原因を3つ挙げましたが、具体的に見ていきたいと思います。
癇癪への対策、それでも癇癪を起してしまった際の対応についても書いていきます!
癇癪の原因

それでは、癇癪の原因についてです。
1歳の発達状況とも絡めながらお話していきますね!
●やりたい!したい!という気持ちが明確になってくる
●手が器用になったり、歩けるようになったり自分でできることが増えてくる
●少しづつ言葉が出てくる
嫌な事・したい事が明確になってくる
今までは、口元にスプーンを運べば口を開けて食べてくれました。
ベビーカーに乗せれば、すんなりと乗ってくれました。
しかし1歳になると、自分のやりたいことや逆にやりたくないことが明確になってきます。
そのため、自分の思った通りにできなかったりすると泣いたり騒いだり癇癪を起したりするようになってきます。
この頃はまだ言葉でのコミュニケーションも十分に取れないので、どうしてもそういった気持ちが行動=癇癪となって表れます。
 Suna
Suna 1歳の長女も、公園から帰りたくない!ベビーカーに乗りたくない!ご飯より遊びたい!という気持ちが出てきたようで、思うようにいかないと癇癪を起すようになってきました。
自分でやりたいのに親が手を出しすぎる
1歳になると、自分でできることが増えてきます。
一人で上手に歩けるようになったり、手先も器用になってきます。
「自分でできる!」「自分で好きにやりたい!」のにパパやママが手伝いすぎたり、手を出しすぎると機嫌を損ねたり癇癪を起すことがあります。
 Suna
Suna 手を繋いで歩く練習をしていたのに、最近、上達してきたからか手を繋ぐのを嫌がるようになってきました。無理に繋ごうとすると癇癪を起します。。まだまだヨチヨチ歩きで親は心配なのですが…
上手にできない
「これがやりたい!」「こうしたい!」と思っても、まだまだ思うように上手にはできないことが多いです。
うまくできなかったり失敗するとひっくり返って癇癪を起すことがあります。
体調が良くない・寒い・暑い・眠い
親の関わり方や子供の成長以外の要因として、体調不良や気温等が挙げられます。
特に、体調があまり良くなかったり暑すぎたりするとイライラして怒りっぽくなる場合があります。
また、遊びすぎて眠かったり疲れていたりするとどうしても癇癪を起しがちになります。
また、のどが渇いたりおなかが空いた時、おやつが欲しい時にも不機嫌になり、気が付くのが遅いとそのまま癇癪に突入することがあります。
暇・遊びたい!
暇だったり、遊びたい時に癇癪を起こすことがあります。
外に出してあげたりお散歩に出かけたり、遊ぶ部屋を変えてあげたりと刺激を与えてあげると機嫌が良くなります!
できることが増え好奇心も旺盛になってくる頃なので、何か楽しいことがしたい!遊びに行きたい!遊んで欲しい!という欲求が出てくるのではないでしょうか?
性格?
癇癪の原因として、もしかしたら『性格』も関係しているのかなぁと思うことがあります。
もしかしたら、おっとりしている子は癇癪の頻度が少なく、意思が強い子や活力が漲っているような子は癇癪の頻度が高かったりするのかなぁ?と思ったりしています。(あくまでも個人の感想です!)
癇癪をなるべく防止するための対策

癇癪を起こす原因が分かったところで、癇癪への対策を考えていきましょう!
成長過程で癇癪を起こすことは仕方のない事ではありますが、できることなら癇癪の頻度を少なくしたいですよね^^;
手を出しすぎず見守る
ヨチヨチ歩きで、まだまだ不器用で、、ついあれこれ手を貸したくなってしまいますよね。
子どもが親の手を払いのける仕草をすることはありませんか?
そういう場合は、大けがをしたり他人に迷惑をかけるような場面でなければ手伝いをしすぎずに後ろから見守ってみてはいかがでしょうか?
やりたいことを気が済むまでさせる
危険でないことや迷惑をかけないことであれば、むやみに止めたり叱ったりせずにしたいようにさせてはいかがでしょうか?
例えば、本棚から本を全部取り出す、おもちゃを全部出す、公園で帰りたくないと泣く…などは、好きなだけさせてあげても何も問題ないと思います。(親は大変ですが…!これでわがままな子になるということはありません。)
いずれもっと言葉が理解できるようになったら、『お片付け』や『されると困る』ことや『時間を決めて遊ぶ』ことを教えても遅くはありません。
ただし、公園で先に遊具を使いたがる、道路で手を繋がない等は外出先で迷惑をかけたり危険が伴うようなことは、癇癪を起こしたとしても言い聞かせる必要があります。
時間に余裕を持ってスケジューリングする
やりたいことを好きなだけさせてあげるには、時間や気持ちに余裕がないと難しいですよね。
特に、公園や児童館で帰りたくない!といつも癇癪を起こすような場合は、時間に余裕を持って早めに行ってガンガン遊ばせると疲れて大人しく帰ってくれることも多いです笑
そのためにも、家事で手を抜けるところは抜いたり、一緒にお昼寝をして体力・気力を回復したりといった細々とした工夫も必要かもしれません…!
また、切り札として赤ちゃん用のおせんべいや、1歳からでも大丈夫なキシリトール菓子を用意しておいて、どうしても帰ってくれない時やベビーカーに乗ってくれない時などにあげるとすんなり帰ってくれる可能性が高いです。
体調や室温等のチェック
なんだかいつもより頻繁に癇癪を起こしたり、機嫌が悪いなと感じた時は体調を気にする必要があります。
熱はないか?気温(室温)はどうか?疲れすぎて眠くなってないか?
機嫌が悪いなと思っていたら、日中はなんともなくても夕方~夜になって熱が出始めた。なんていうパターンも聞きますので、いつもより少し気にして見ていてもいいかもしれません。
前向きな声掛け・おおらかな気持ちで見守る
1歳児の癇癪は、成長とともに落ち着いてきます。
言葉が上手になってくると、癇癪ではなく言葉で伝えてくれるようになってくるからです。
いずれは落ち着くと思って、あまり深く悩まずに前向きな声掛けをしつつおおらかな気持ちでやり過ごしましょう!
多くの「ダメ!」を言うよりも、危険がなく迷惑をかけない場面では見守ることも大切です。
癇癪を起こしてしまった時の対応

対策を講じていても、癇癪を0にすることは不可能に近いと言えます。
癇癪を起こしてしまった際、どのように対応すればいいでしょうか?
子どもに寄り添いながらも、なるべく自身のストレスにならないように対応することがポイントだと考えています。
気持ちに寄り添う声掛け
癇癪を起こされると、イライラして「またか…」と思ってしまうこともありますが、なるべく子どもの気持ちに寄り添うような声掛けをするようにしましょう。
「これがやりたかったんだね。でも、もう帰る時間なんだ」や「うまくできなくて泣いてるのね。がんばったね。」など!
落ち着いたトーンで話しかけることで、早めに子どもの気持ちも落ち着いてくれると思います。
抱っこする
時には、声をかけるだけでなく抱っこして背中をトントンしてあげることで早めに気持ちを落ち着かせてくれることもあります。
抱っこしてユラユラしてあげるのが好きな子もいるので、その子の気に入る方法で抱っこしてあげると効果がアップすると思います!
放っておく時間が必要な時も
声をかけてあげたり、抱っこしてあげても癇癪が収まらないこともあります。
そんな時は、少しの間だけそっとしておく方が良い場合もあります。
目の届く範囲で周りに危険がない場合に限りますが…!
実際には、そっとしておいても癇癪が終わらないことも多々ありますよね。。癇癪→声掛けや抱っこ→そっとしておく→声掛け…を繰り返すしかない場合も結構あります。
外へ出かけてみる・遊ぶ部屋を変えてみる
暇だったり遊びたくて癇癪を起こしている場合もあるので、おなかも空いていない、体調も悪くない、眠くないはずなのに癇癪を起こしている時は気分転換も兼ねて外へ出かけてみてはいかがでしょうか?
天気や季節によっては外に出られな時もあると思うので、遊ぶ部屋を変えてみるだけでも機嫌が直ることもありますよ!
癇癪はいつまで続く?

では、1歳過ぎたあたりから始まった癇癪はいつごろまで続くのでしょうか。
思い出してほしいのが、この後に来るであろう2歳のイヤイヤ期です。
イヤイヤ期は育児書などを参考にすると『1歳後半~3歳ころまで』続く子が多いようなんですね。
そうすると、1歳時点で始まった癇癪は…終わらずにそのままイヤイヤ期に突入する可能性が高いとみた方がいいでしょう…。
 Suna
Suna このままイヤイヤ期に突入と聞いて『ガーン』と思った人もいるかもしれません。でも、次の体験談に詳しく書きますが、このまま癇癪がひどくなっていくばかりでもありませんので、希望を捨てないでください…!
体験談
我が家では4歳の長男と1歳の長女がいます。
現在1歳の長女は、ここ最近癇癪を起こすことが増えてきました。
2人の1歳~イヤイヤ期にかけての体験談を簡単にですがお話しますので、少しでも参考になればうれしいです♪
【長男:1歳の時の癇癪】怒りポイント

まず、長男ですが1歳のお誕生日を境に怒ったり癇癪を起こす頻度が上がってきました。
何となく不機嫌な時も増えたように感じました。
長男の怒りポイントは主に
①たくさん抱っこしてほしいのにしてくれない時。
②外に行きたいのにいけない時。
③公園から帰りたくない時。
の3つでした。
癇癪への対応
長男は、声掛けやそっとしておくことはほとんど効果がなく、抱っこするか本人の好きなようにやらせるかでしか癇癪は収まりませんでした。
本人が外に行きたがったら雨でも台風でも抱っこ紐やベビーカーで散歩に行きました。
公園には朝っぱらから出かけて、本人が疲れて帰りたくなるまでいました。
抱っこだけは2歳過ぎまでしょっちゅうしたがったので、しんどかったですが抱っこ紐を使ったりベビーカーでなるべく外出したりしつつやり過ごしました。
いつまで続いた?
いつまでこれが続くんだろう?と毎日思っていましたが、2歳半あたりからは癇癪はほとんどなくなりました。
公園遊びもタイミングを見て声をかけるとちゃんと帰るようになりました!
これまでが大変すぎた分(?)イヤイヤ期はあったのですが、正直2歳過ぎたあたりから楽になったなぁ~と感じていました。
ちなみに、3歳過ぎてからは雨だったり寒い日や暑い日は外に行きたがらなくなりました笑
驚くほど落ち着きました。
【長女:1歳の癇癪】怒りポイント

長女は現在1歳3ヶ月なので、まだまだ癇癪は始まったばかりなのですが、怒りのポイントは長男とは異なっています。
①遊んで欲しいのに遊んでくれない時・外遊びがしたい時
②上手にできなかったとき
③必要以上に手伝いをされそうになった時
長男と比べると、自分で好きにやりたい。上手にやりたい。という気持ちが強いようです。
癇癪時の対応
家事や食事中など遊べない時に遊んで欲しいと来られると困ってしまうんですよね…。
仕方ないので短時間だけ教育TVを付けて見せています。
また、やらなくてはいけないことを早めに切り上げて遊びに付き合うようにしています。
危険や迷惑が掛からないような場面では、手を放してなるべく好きなように行動させています。
癇癪を起こしてしまった際には、声をかけつつそっとしておくと気分を切り替えて遊び出すことが多いです。
兄妹でも、癇癪を起こすポイントや癇癪時の効果的な対応が違っています。その子に合った対応や対策が必要なんですね!
癇癪に耐えられないと思ったら…

いつかは終わると思っていても、しょっちゅう不機嫌になられたり癇癪を起こされるとストレスが溜まりますよね。
もう癇癪に耐えられないと思ったら、一旦立ち止まって自分を労わってほしいです。
「よく頑張ってるよ」と自分を褒めてあげる
子どもの癇癪に優しく根気よく付き合うのって、本当にすごく大変で疲れることだと思います。
それを何回もやっているパパやママが「もう耐えられない!」と思うのは当たり前です。
そんな時は、自分自身を「よく頑張ってるよ」「疲れたよね。」と頑張りや疲れをまずは認めてあげましょう!
 Suna
Suna 毎日、子どもと真剣に向き合っているパパやママ、本当に尊敬します。
癇癪は今だけと受け入れる
「こんなこと、いつまで続くんだろう?」何度もそう思わされてしまうこともあると思います。
でも、子供が癇癪を起こすのってこれからの長い人生の中で今だけなんですよね。
怒ったり泣いたりすることがあっても、癇癪をこんなにたくさん親の前で起こすのは1~3年程度です。
そのうち親の前では、怒りや泣くと言った感情をストレートには出さなくなってきます。
子どものストレートな感情を受け止めてあげられる期間は案外短いと思えば、癇癪も貴重なものに思えてくるかもしれません。
子どもと少し離れる時間を作る
休日に子どもと半日くらい離れる時間を作ることができると、気持ちが少し回復します。
家で好きなことをしてもいいし、マッサージを受けに行ってもいいし、ショッピングやカフェでもいいので好きなように過ごしてみましょう。
そのためには、家族の協力が不可欠です。
できれば、月に何回と決めて、月に最低1回はフリーで行動できる時間をお互いに持つことができるとリフレッシュ効果が上がると思います!
日常の中で息抜きする
ストレスにはやっぱり息抜きが効果的ですよね!
本当は1日中、何も考えなくていい自由な時間があったらいいですが、なかなかそうもいかなかったり、1日息抜きしてもすぐにストレスが溜まったりすることもありますね。
日常の中でちょいちょいできる息抜きをいくつか用意しておくといいかもしれません。
DVDや小説などは、途中で子供に中断されるとイラっと来ることがあり、結局ストレスが溜まってしまう可能性があるのであまりおすすめしません。
●散歩のついでに寄れるお店を探しておく
●室内でお気に入りの曲を流しておく
●子どもと一緒にお昼寝する
●大人用ぬりえ
など…
癇癪ばかりなのは発達障害だから?

癇癪ばかり起していると、『発達障害』なんじゃないか?と心配になることもあると思います。
癇癪は発達障害の特性ではないので、癇癪が多いからと言って発達障害とは言い切れません。
ただし、発達障害の子供に良くみられる傾向として以下の4つが挙げられますが、それが原因となって癇癪を起こすことがあります。
2.自分の意思や気持ちを他者に伝えるのが苦手
3.他者と自分の意図をすり合わせるのが苦手
4.気持ちのコントロールが難しい
癇癪が多いだけで発達障害と決めつけることはできません。
もし、他にも心配なことがあれば小児科の先生や役所の児童支援課等に相談してみてくださいね!
【癇癪とは?】癇癪の定義
癇癪(かんしゃく)とは、声を荒げて泣いたり、激しく奇声を発したりするなどの興奮を伴う混乱状態を指します。
通常時の不機嫌や泣いたり怒ったりがエスカレートしたイメージです。
気持ちのコントロールがうまくできない時や、言葉で上手に伝えることができない時に起こりやすいです。
まとめ
1歳過ぎたあたりから増え始める癇癪。
原因と対策・対応を知って少しでも気持ちを楽に過ごせたらいいですね!
原因は様々ですが、時期が過ぎれば必ず落ち着いてくるのでそれまでの辛抱です。
頻度は違えど大抵の子は1歳~3歳ころまでの間、イヤイヤ期を含め癇癪を超しがちな時期があるものです。
3歳くらいになれば、驚くほど成長して言葉も動きもしっかりしてきます。
親子でのやり取りもますますスムーズになって、子育ても楽しくなってきますよ♪